2022年05月05日
螺鈿三段箱の修理⑲ 螺鈿接着(本番)・・・
螺鈿三段箱の修理⑲ 螺鈿接着(本番)・・・
いよいよ欠損螺鈿の膠接着本番です。
先日作った膠や、膠練り砥の粉(膠粘土)は、
日が経って劣化している可能性もありますので、
ここは慎重を期して新しく作り直すことにしました。

まずは膠の原材料を用意。

またしても、ミニミニ鋸刃くんが登場!
これがまたハマりまして、研磨粉や微差カットで
加工しにくかった膠を細かく出来るわけであります!!
ホント活躍の場が広がりますね(^.^)

この小さくした膠たちを容器へ、、、

水を垂らします。。。

ここでお湯を溜めた魔法瓶を用意。
もう一つの魔法瓶にもあっつ熱のお湯を準備。
膠溶かすのに温度管理大切ですね。

はい、調整しながら溶かして~~トロトロに。
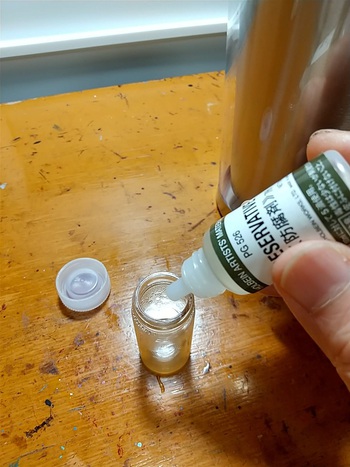
良い感じになったところで、防腐剤1滴垂らしておきましょう。
さ~いよいよ接着です。
膠の作業は時間勝負!手早くやらないとすぐ固まって来ます。
温めといて~欠損部にチョンと塗り、
サッと螺鈿を置いてブニュッと押し付ける。。。
そんな感じですので、写真を撮る余裕があまりありません(^^;

例の目立つ螺鈿の押し付けた様子。
ブニュッと膠がはみ出た感じがお分かりかと思います。

上蓋の数ある欠損部のラスト貼付まで来ました!
岩山の輪郭螺鈿は、膠粘土を塗って、、、

ハイ!OK、、、、と言いたいところでしたが、
余りにも茶色っぽいですね~(^^;
膠粘土を厚塗りし過ぎたようです。
この後、一旦ドライヤーで温めて剥がして貼り直し。
もう少し膠粘土を薄く塗って、
下地の錆がちょっと斑に見えるようにしました。
このように一発OK!となず、やり直しケースが多いのが、
経年変化のある品物の修理の特徴と言えるでしょう。

きれいにし過ぎてもダメ、風合いが似なくてはダメ!
というのが難しいところであります(^^;
つづく。。。
いよいよ欠損螺鈿の膠接着本番です。
先日作った膠や、膠練り砥の粉(膠粘土)は、
日が経って劣化している可能性もありますので、
ここは慎重を期して新しく作り直すことにしました。
まずは膠の原材料を用意。
またしても、ミニミニ鋸刃くんが登場!
これがまたハマりまして、研磨粉や微差カットで
加工しにくかった膠を細かく出来るわけであります!!
ホント活躍の場が広がりますね(^.^)
この小さくした膠たちを容器へ、、、
水を垂らします。。。
ここでお湯を溜めた魔法瓶を用意。
もう一つの魔法瓶にもあっつ熱のお湯を準備。
膠溶かすのに温度管理大切ですね。
はい、調整しながら溶かして~~トロトロに。
良い感じになったところで、防腐剤1滴垂らしておきましょう。
さ~いよいよ接着です。
膠の作業は時間勝負!手早くやらないとすぐ固まって来ます。
温めといて~欠損部にチョンと塗り、
サッと螺鈿を置いてブニュッと押し付ける。。。
そんな感じですので、写真を撮る余裕があまりありません(^^;
例の目立つ螺鈿の押し付けた様子。
ブニュッと膠がはみ出た感じがお分かりかと思います。
上蓋の数ある欠損部のラスト貼付まで来ました!
岩山の輪郭螺鈿は、膠粘土を塗って、、、
ハイ!OK、、、、と言いたいところでしたが、
余りにも茶色っぽいですね~(^^;
膠粘土を厚塗りし過ぎたようです。
この後、一旦ドライヤーで温めて剥がして貼り直し。
もう少し膠粘土を薄く塗って、
下地の錆がちょっと斑に見えるようにしました。
このように一発OK!となず、やり直しケースが多いのが、
経年変化のある品物の修理の特徴と言えるでしょう。
きれいにし過ぎてもダメ、風合いが似なくてはダメ!
というのが難しいところであります(^^;
つづく。。。


